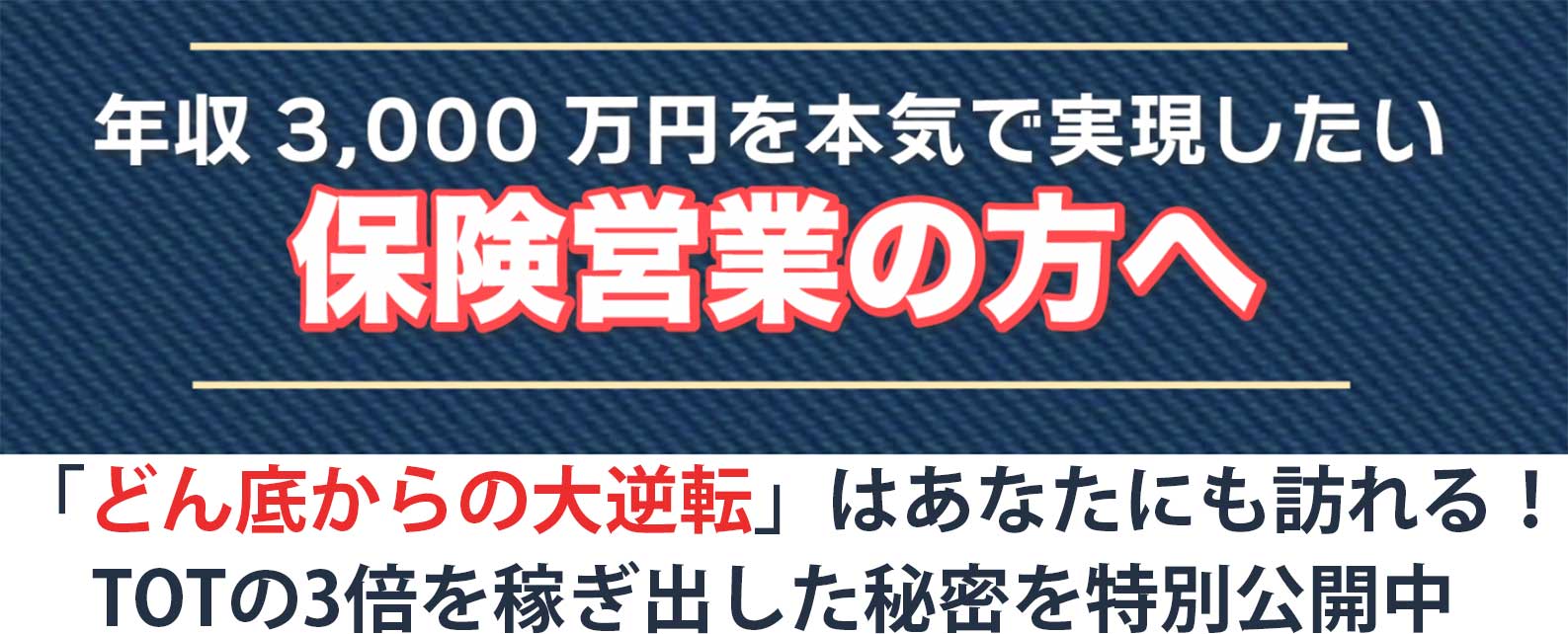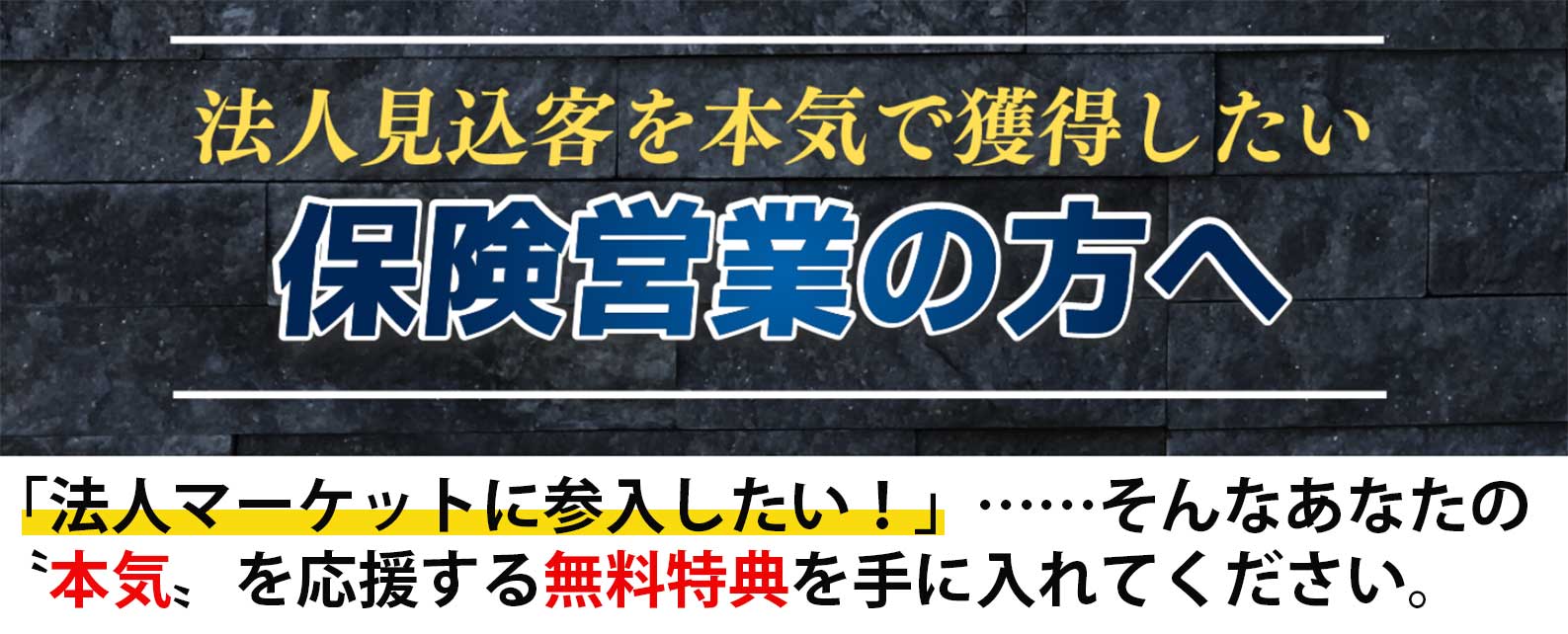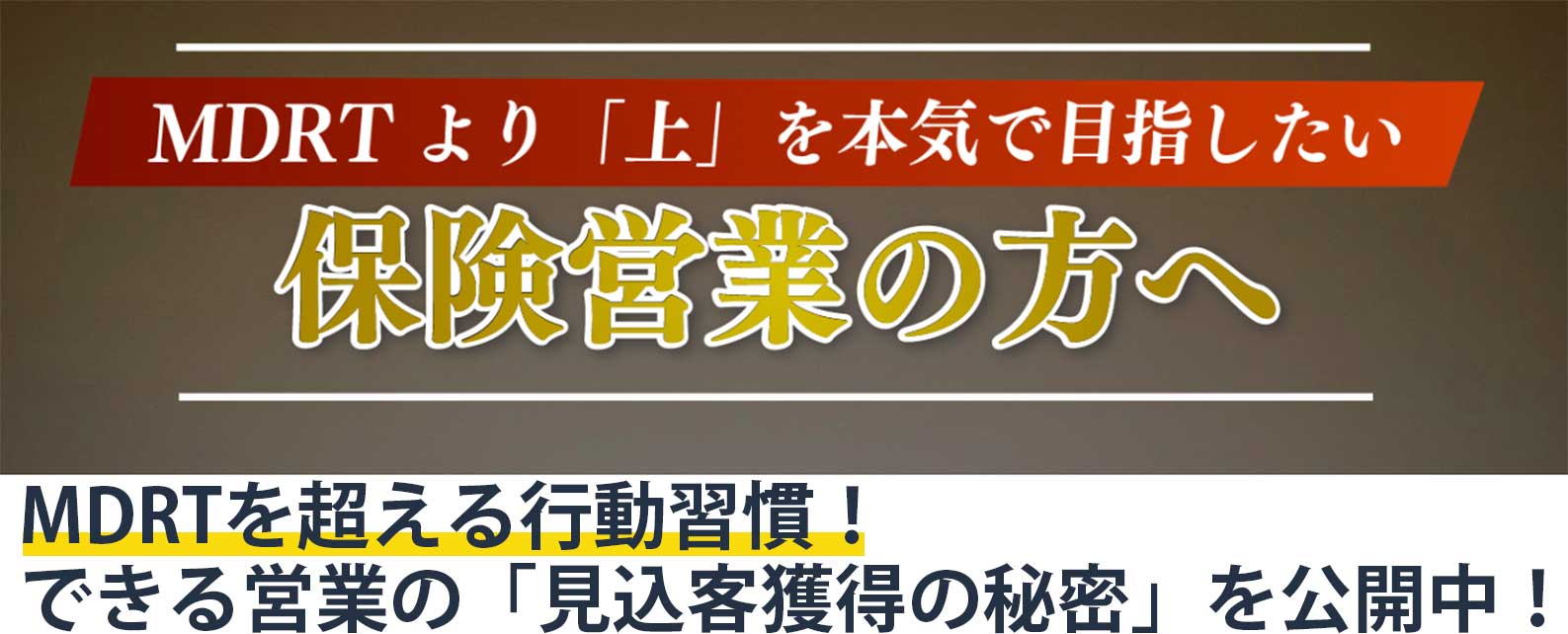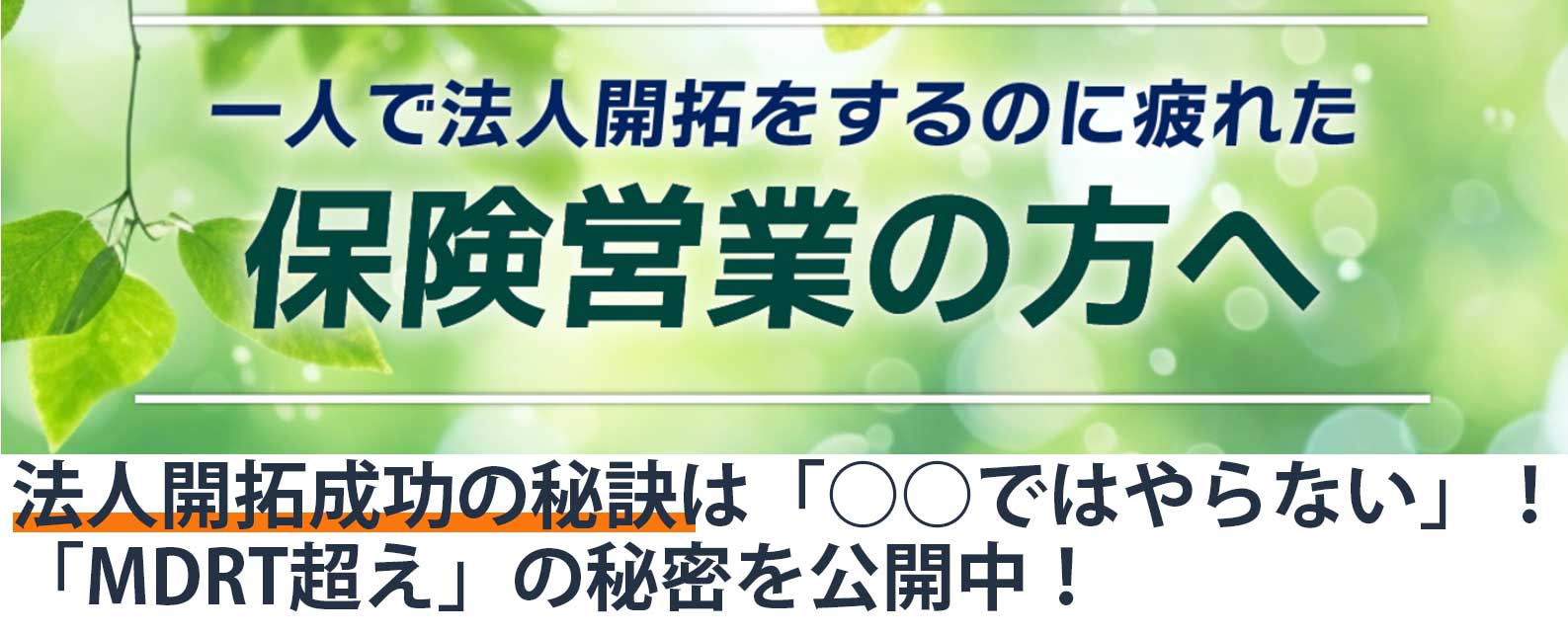皆さんは日々の仕事の目標の先、仕事のゴールを決めていますか?
ゴールを決めてコツコツと努力しているのに、何だかうまくいかない。
やる気が思うように出ない…と悩んでいませんか?
もしかすると、良くないゴール設定をしていることが原因かもしれません。
今回は「年収をゴール設定にすると失敗する」について解説します。
一見すると良いゴール設定に見える
皆さんは「年収500万円の人が年収1億円を目指す」というゴール設定の例をどう思いますか?
この例をコーチングのゴール設定と目標設定の違いとは?ゴール設定で理想に近付こう!の内容に当てはめて考えると、年収500万円の人が年収1億円を達成するには、コンフォートゾーンを脱出する必要があります。
一見すると、ゴールとして相応しく感じます。
ですが、この年収1億円ゴールは仕事のゴールとして非常に不適格なのです。
ラーニングゾーンに挑戦するような高い理想なのに、なぜ仕事のゴールとして不適格なのか。
その理由を見ていきます。
年収を仕事のゴールにしてはいけない2つの理由
▼1億円そのものに意味はない、お金は燃料
単に年収1億円を目指すだけでは意味がありません。
ゴールの意味を見出すには、手に入った1億円を何に使うか、1億円で何がしたいのか。これが明確になっていることが重要です。
お金は言わば燃料(エネルギー)です。燃料をただ貯めただけでは、何の意味もないですよね。
燃料を使って車を動かしたいのか、動かした車でどこへ行きたいのか。
お金も同じように、使い道(行動目標)を具体的にしておくことが大切です。
▼他者の価値観が入り込んでしまう
仕事のゴール設定では「本気でやりたい」という意志を主軸にすることが大切です。
しかし、現代社会を生きていれば、必ずどこかで他者の価値観が刷り込まれているもの。
良い年収を目指すだけのゴールは他のゴールと比べて、こうした他者の価値観に影響されやすい欠点があります。
無意識に刷り込まれた「稼いで人からよく見られたい」「売れなくなったと思われたくない」といった周囲の視線・価値観の影響により、無自覚に周囲の評価を気にしたゴール設定をしやすいのです。
以上のことから、年収を仕事のゴールにするのは不適格と言えます。
加えて、他者の価値観に基づく行動はやる気が湧きづらい上に、やる気を燃やしにくいデメリットがあります。
故に、明確な金銭の活用方法と、他者の価値観が入りにくいゴールを設定することが大切です。
仕事とファイナンスのゴールを分けて設定しよう
それでは、どのようなゴールの立て方が良いのでしょうか。
解決策として、仕事とファイナンスのゴールを別々に設定する方法があります。
仕事のゴール設定については、これまで説明してきた通り。資金で何をするのか、目標金額を生み出すビジネスモデルを作るといった具体的な行動目標が重要です。
ならばファイナンスのゴール設定とは何か。ゴールとして機能するのか。
例を用いて説明しましょう。
「東京23区内の新築タワーマンションを買いたい」という夢を叶えるため、ファイナンスのゴールとして年収1億円を設定した場合。
この場合、理想のライフステージを実現させたい願望があること、そのために年収1億円が必要なことが分かります。
つまり、年収1億円で何をしたいのか明白にしている、他者の価値観に左右されていない状態であり、先述した2つの理由をクリアしているのです。
よって年収をファイナンスのゴールにしても、問題なく機能します。
このように2つのゴールを個別に設けることで、それぞれ具体的にどんな過程が必要か分かってきます。
具体的な計画を立てると、モチベーションの維持が容易になり、やる気に満ちた行動を取りやすくなるでしょう。
まとめ
今回は年収は仕事のゴールには不適格なこと、仕事とファイナンスに分けてゴールを設定することについて解説しました。
長々と述べてきましたが、これまでの内容は心理学でも説明ができます。
人間の動機付けには2種類あり、外発的動機付けと内発的動機付けがあります。
外発的動機付けは、報酬や周囲からの評価といった外からの働きかけによって生じる動機付け。
内発的動機付けは、自身の強い興味、探究心、向上心等の内面的な働きによって生じる動機付けです。
今回の内容に照らし合わせると、他者の価値観を意識したゴール設定は外発的動機付けであり、自分の願望によるゴール設定は内発的動機付けに当てはまります。
つまり、ゴール設定では内発的動機を重要視することが大切なのです。
内発的動機を意識して、仕事とファイナンスのゴールを上手く使い分けること。
こちらを覚えていただき、今後のゴール設定に活かしていただけると幸いです。